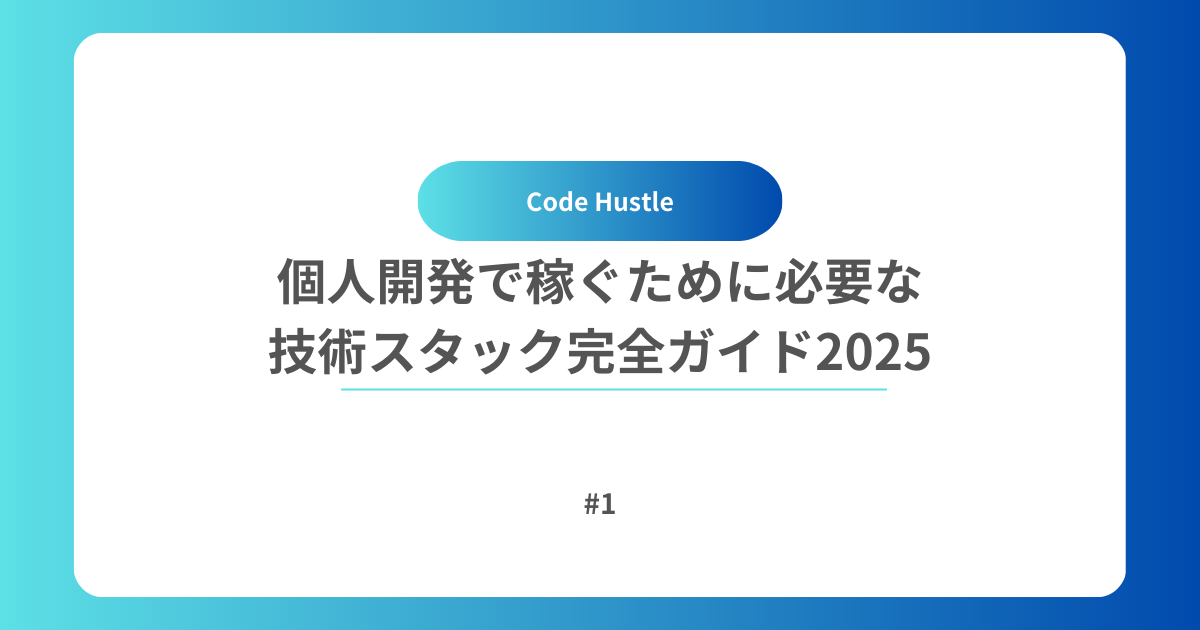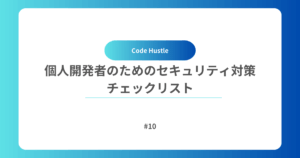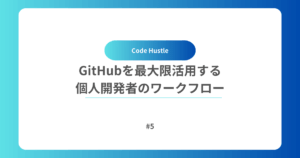個人開発の技術選びって難しい。選択肢が多すぎて何から手を付けていいか分からなくなる。
実際、個人開発界隈を見てると、技術選びで失敗して挫折する人がめちゃくちゃ多い。最新技術を追いかけまくって何も完成しないパターンとか、複雑すぎるアーキテクチャ組んで保守できなくなるパターンとか。
一方で成功してる個人開発者を見ると、使ってる技術って意外とシンプル。むしろ「えっ、それだけ?」って思うくらい絞り込んでる。
ということで、実際に収益化に成功してる個人開発者たちが使ってる技術スタックをまとめた。
技術選びを間違えると詰む理由
個人開発における技術選択って、企業での開発とは全く違う。
企業なら分業できるけど、個人開発は全部一人でやる必要がある。フロントもバックもインフラも全部。だから学習コストが高い技術を選ぶと、いつまで経ってもリリースできない。
よくあるのが、マイクロサービスアーキテクチャで作り始めて挫折するパターン。ある個人開発者は「最初のプロジェクトをマイクロサービスで作って、複雑すぎて3ヶ月で投げた」って言ってた。
個人開発は保守も自分でやることになる。複雑な技術スタック組むと、3ヶ月後の自分が理解できなくて詰む。これマジでよくある話。
要するに個人開発の技術選びは「いかにシンプルに作るか」が全て。カッコいい技術より、枯れた技術で確実に動くものを作る方が100倍大事なんだ。
フロントエンドは3パターンから選べ
成功してる個人開発者のフロントエンド選択を分析すると、大体この3パターンに収まる。
1. Next.js + Tailwind CSS(7割がこれ)
圧倒的に多いのがこの組み合わせ。Next.jsならルーティングもSSRもAPI作成も全部入り。Tailwind CSSと組み合わせれば、デザインで悩む時間もゼロ。
有名な個人開発サービスの大半がこの技術スタック。プロトタイプから本番まで同じコードで行けるから、作り直しのコストが発生しないのが強み。
2. 素のHTML/CSS/JavaScript(意外と多い)
「は?今更?」って思うかもしれないけど、シンプルなツール系ならこれで十分。
実際、月数万円稼いでるツール系サービスで、jQuery使ってるだけってケース結構ある。ランディングページとか、機能が少ないサービスなら下手にフレームワーク使うより早い。
ある開発者は「最初に収益化できたサービスはHTML/CSS/jQueryだけで作った。今も月3万円稼いでる」って言ってた。
3. Bubble / Webflow(プログラマーでも使う)
ノーコードツールをバカにしてる人多いけど、MVP検証には最適。
プログラミングできる人でも、アイデア検証にはノーコード使うケースが増えてる。1週間で作って反応見て、良さそうなら本格開発するパターン。時間の節約になるらしい。
バックエンドは用途で選べ
バックエンドも成功パターンは決まってる。
1. Next.js API Routes + Prisma(最多)
フロントでNext.js使うならバックエンドも同じにすればいい。コードベース1つで管理楽だし、TypeScriptで型安全。Vercelにデプロイすればインフラ管理も不要。
個人開発界隈では「これだけで9割のWebサービスは作れる」って言われてる。実際その通り。
2. FastAPI(Python勢)
機械学習とか複雑なデータ処理が必要ならPythonのFastAPI。学習コスト低いし、ドキュメント自動生成されるのも地味に便利。
ただし、フロントエンドと言語が分かれるから管理が面倒。本当に必要な時だけ使うべきって意見が多い。
3. Firebase(スピード重視)
認証もDBもストレージも全部入り。料金も従量課金だから初期コストゼロ。
ただしベンダーロックインがキツい。「Firebaseで作ったサービスを後から移行しようとして地獄を見た」って話はよく聞く。最初から心中する覚悟が必要。
データベースとインフラの正解
個人開発のインフラコストは収益を圧迫する。賢く選ばないと赤字になる。
データベース
PostgreSQL一択って意見が圧倒的。汎用的で実績もある。Supabaseなら認証機能付きで無料枠も充実。
NoSQL使いたくなる気持ちは分かるけど、「99%のケースでRDBで事足りる」ってのが個人開発界隈の共通認識。無駄に複雑にするな。
ホスティング
Vercel、Netlify、Railwayが人気トップ3。どれも無料枠あるし、デプロイも簡単。
最近はVercelの無料枠制限がキツくなってきたから、Netlifyに移行する人も増えてる。Railwayは従量課金で初期は激安。
その他必須ツール
成功してる個人開発者が共通して使ってるツール:
- GitHub(バージョン管理)
- GitHub Actions(CI/CD)
- Sentry(エラー監視)
- Google Analytics(アクセス解析)
- Stripe(決済)
これだけあれば十分。他は必要になってから追加すればいいって意見が多い。
よくある技術選択の失敗
個人開発界隈でよく聞く失敗パターンをまとめた。
最新技術を追いかける病
新しい技術使いたくなる気持ちは分かる。でも収益化が目的なら枯れた技術使えってのが鉄則。
「Deno使ったりSvelteKit使ったりしたけど、情報少なくて詰んだ。結局Next.jsに戻った」って話はあるある。
過度な最適化
最初から100万PV耐えられる設計とか要らない。まず100人集めることを考えろってよく言われる。
マイクロサービスとか、GraphQLとか、Kubernetesとか、個人開発には過剰。モノリシックで十分。
フルスタックフレームワークを避ける
「Next.jsは重い」とか言ってる場合じゃない。個人開発は開発速度が全て。多少重くても早くリリースできる方が100倍マシ。
2025年のトレンドとAI活用
2025年はAI統合が当たり前になった。成功してる個人開発者はほぼ全員AI API使ってる。
OpenAI API、Claude API、Gemini APIを使えば、一人でも高機能なサービスが作れる。月10ドルで賢いAIが使い放題とか、使わない手はない。
エッジコンピューティングも普及してきた。Cloudflare WorkersとかDeno Deployとか、ユーザーに近い場所でコード実行できる。個人開発には最適って評判。
まとめ
個人開発の技術スタックは、シンプルが正義。
成功してる個人開発者の多くが「Next.js + Tailwind + Vercel + Supabase」の組み合わせ。これだけで大体のサービスは作れる。
技術選びに迷ったら「3ヶ月でリリースできるか?」を基準にしろってのが鉄則。できないなら、もっとシンプルな選択肢を選べ。
最新技術とか複雑なアーキテクチャとか、収益化してから考えればいい。まずは動くものを作って、ユーザーの反応を見る。これが個人開発で成功する人たちの共通点なんだ。