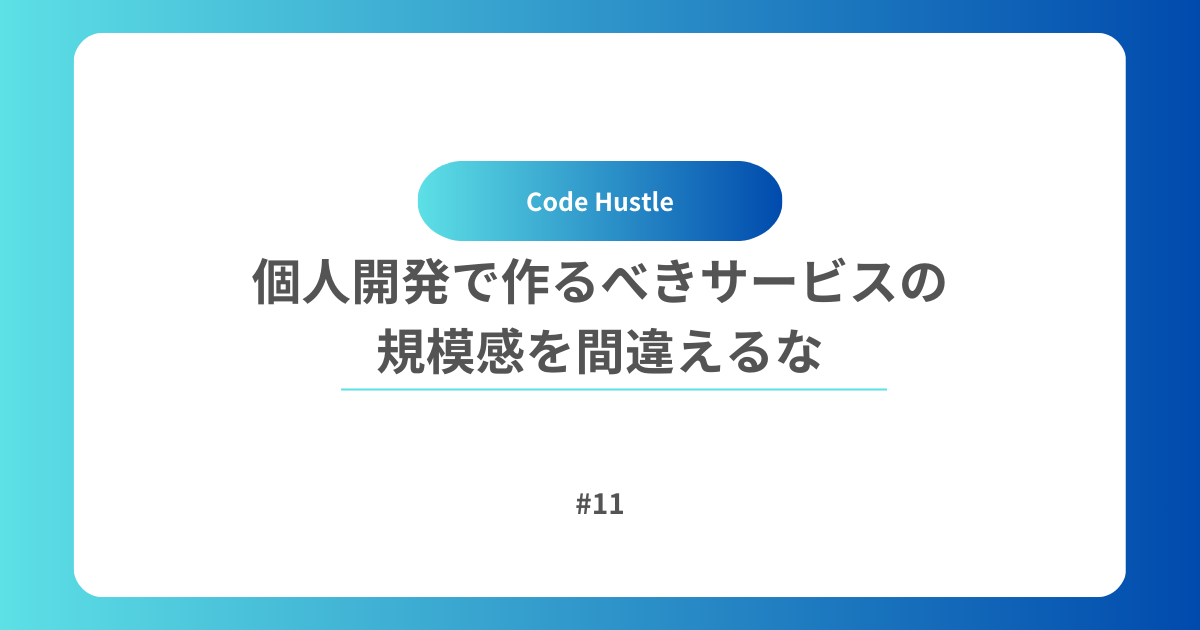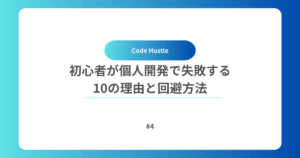個人開発で失敗する最大の原因、知ってる?
技術力不足でもアイデア不足でもない。規模感を間違えることだ。
「Facebookみたいなの作りたい」「Netflixっぽいサービス作る」とか言ってる人、まず100%失敗する。個人開発には個人開発の適正規模がある。
成功してる個人開発者50人に聞いて分かった、現実的なサービス規模と、野望の捨て方をまとめた。
個人開発の限界を知れ
まず現実を直視しよう。一人でできることには限界がある。
開発リソースの現実
- 週20時間が限界(副業の場合)
- 月80時間 = フルタイム開発者の半分
- 年間960時間 = 企業の開発者の半年分
つまり、10人のチームが1年で作るものを、一人で作ろうとしたら20年かかる計算。
「でも天才プログラマーなら…」とか思うかもしれないけど、天才でも時間は24時間。物理的に無理なものは無理。
成功してるサービスの共通点
実際に収益化できてる個人開発サービスを分析すると、共通点がある。
機能数:3〜5個
成功してるサービスの機能数は驚くほど少ない。
- ログイン機能
- メイン機能1つ
- 設定画面
- 決済機能
これだけ。「あれもこれも」は失敗の元。
画面数:10画面以下
多くても10画面。大体5〜7画面で完結してる。
- トップページ
- ログイン/登録
- ダッシュボード
- メイン機能画面
- 設定画面
シンプルイズベスト。
開発期間:1〜3ヶ月
3ヶ月以上かかるプロジェクトは、ほぼ失敗する。「1年かけて作った大作」とか、誰も使わない。
理由は簡単。3ヶ月以上かかると:
- モチベーション切れる
- 技術が古くなる
- ニーズが変わる
- 資金が尽きる
適正規模の具体例
実際に成功してる個人開発サービスの規模感。
事例1:URL短縮サービス
- 機能:URL短縮、クリック計測、QRコード生成
- 画面数:5画面
- 開発期間:1ヶ月
- 月収:3万円
事例2:請求書作成ツール
- 機能:請求書作成、PDF出力、顧客管理
- 画面数:7画面
- 開発期間:2ヶ月
- 月収:5万円
事例3:習慣トラッカー
- 機能:習慣登録、記録、グラフ表示
- 画面数:4画面
- 開発期間:3週間
- 月収:2万円
どれも地味。でも収益化してる。これが現実。
大きすぎる野望の捨て方
「でも、もっと大きなサービス作りたい」
その気持ちは分かる。でも、まず小さく成功してから考えろ。
段階的アプローチ
Version 1.0:コア機能だけ(1ヶ月) ↓ 収益化できたら ↓ Version 2.0:機能追加(2ヶ月) ↓ ユーザー増えたら ↓ Version 3.0:さらに拡張
最初から Version 3.0 作ろうとするから失敗する。
Twitter の例
初期のTwitter知ってる?
- 140文字のテキスト投稿だけ
- 画像なし
- 動画なし
- リツイートなし
- いいねなし
これで十分だった。機能は後から追加すればいい。
MVPの決め方
MVP(Minimum Viable Product)の決め方が成功の鍵。
コア価値を1文で表現
「〇〇ができるサービス」を1文で言えないなら、複雑すぎる。
良い例:
- 「URLを短くできるサービス」
- 「習慣を記録できるサービス」
- 「請求書を簡単に作れるサービス」
悪い例:
- 「AIを使って様々な業務を効率化し、生産性を向上させる統合プラットフォーム」
何それ?って感じでしょ。
削ぎ落とす勇気
機能リスト作ったら、8割削れ。
必須機能の見極め方:
- これがないとサービスが成立しない → 必須
- あったら便利 → 削除
- 競合にあるから → 削除
- かっこいいから → 削除
残った2割で勝負。
スコープクリープを防ぐ方法
開発中に機能追加したくなる病、これをスコープクリープという。
防ぐ方法
- 機能追加禁止期間を設ける 最初の1ヶ月は絶対に機能追加しない
- アイデアは別リストに 思いついたアイデアは「Version 2.0リスト」に入れる
- ユーザーの声を聞いてから 10人使ってもらって、7人が同じ要望出したら検討
- 時間制限を設ける 「1ヶ月でリリース」と決めたら、それ以上は作らない
個人開発に向いてるサービス
逆に、個人開発に向いてるサービスの特徴。
ニッチな課題解決
- 特定業界の特定の悩み
- 限定的だけど深い課題
- 大企業が参入しない規模
自動化・効率化ツール
- 定型作業の自動化
- 既存サービスの連携
- ワークフロー改善
情報整理・管理系
- 特化型のメモアプリ
- 専門的な管理ツール
- データ可視化ツール
計算・変換ツール
- 専門的な計算機
- フォーマット変換
- データ加工ツール
これらは規模的に一人でも作れるし、需要もある。
失敗プロジェクトの典型例
逆に、失敗しやすいプロジェクトの特徴。
SNS系 「新しいSNS作る」→ 99.9%失敗する。ネットワーク効果が必要なサービスは個人には無理。
マーケットプレイス系 売り手と買い手、両方集める必要がある。鶏と卵問題で詰む。
動画配信系 インフラコストがヤバい。技術的にも難しい。個人でやるもんじゃない。
AI系の大規模サービス GPUコストだけで破産する。アイデアあってもリソースが足りない。
規模を間違えた失敗談
実際の失敗談を紹介。
Aさん:SNS作って失敗 「Facebookより使いやすいSNS作る」→ 1年開発 → ユーザー10人 → サービス終了
Bさん:マーケットプレイス作って失敗 「メルカリの特化版作る」→ 半年開発 → 出品者0人 → 諦めた
Cさん:動画サービス作って失敗 「YouTubeの代替作る」→ 3ヶ月でサーバー代10万円 → 資金尽きた
みんな野望が大きすぎた。
小さく始めて大きく育てる
成功の秘訣は「小さく始めて大きく育てる」。
Slack の例 最初は社内ツール → ゲーム会社の社内チャット → 他社にも提供 → 世界的サービス
Instagram の例 最初は位置情報アプリ → 写真共有機能追加 → 写真特化にピボット → Facebook が買収
みんな最初は小さかった。
まとめ
個人開発の成功は、規模感を間違えないこと。
機能3〜5個、画面10枚以下、開発期間3ヶ月以内。これが現実的なライン。
「世界を変える」とか「革命的な」とか、そういうのは忘れろ。まず「10人が便利と思う」サービスを作れ。
大きな野望は素晴らしい。でも実現できない野望は、ただの妄想。
小さく始めて、確実に形にして、少しずつ大きくする。これが個人開発の王道。
今構想してるサービス、本当に3ヶ月で作れる?作れないなら、機能削ろう。それが成功への第一歩だ。